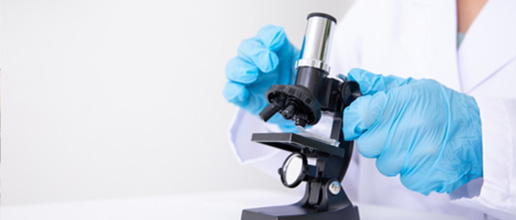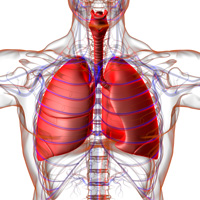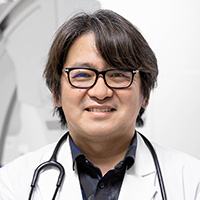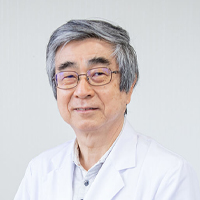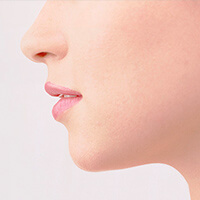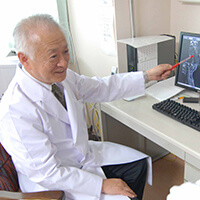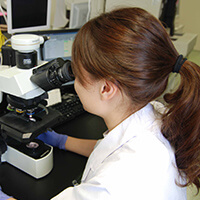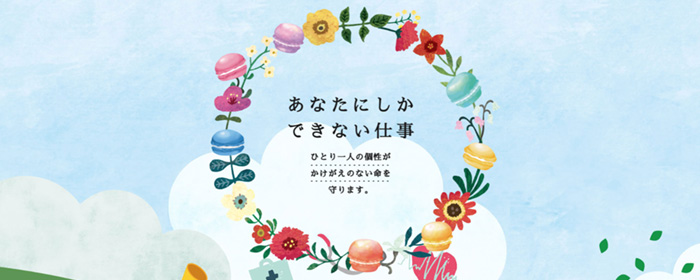8.しゃっくり研究の未来・他分野での応用
しゃっくり研究の未来・他分野での応用
※この章の情報は全て筆者個人の見解です。
- 仮説1:誤嚥性肺炎は横隔膜の筋力回復によって改善するかもしれない
- 仮説2:機能性胃腸障害の治療にアセトアミノフェンが有効かもしれない
- 仮説3:100m全力疾走したら、しゃっくりが止まるかもしれない
理由仮説1
横隔膜方式にょる呼吸法・哺乳法は哺乳類特有のものである事から「横隔膜は気体または液体を体内に吸い込むため、陰圧を作る臓器である」という前提が成り立つかもしれません。
横隔膜だけを鍛える方法はまだありませんが、深呼吸などによる筋力回復により、誤嚥予防ができる様になるかもしれませんね。
理由仮説2
しゃっくり治療を通じて実感することは、どうやら「食道粘膜下の慢性炎症」はアセトアミノフェンによって軽減されるようだ、という感触です。
現時点で機能性胃腸障害は本人の感覚以外は、客観的に判定する手段がほぼないようです。しかし何らかの微妙な炎症を、患者さんが敏感に感じ取っている可能性は高いと思います。実際、機能性胃腸障害らしい症状から止まらないしゃっくりに悩む40代女性が少なからずおられます。しゃっくりのメカニズムから演繹すると、機能性胃腸障害にアセトアミノフェンが有効である可能性はあると思います。
理由仮説3
普段、呼気中に含まれるCO2濃度は、4~5%程度です。一方全力疾走して息切れした時は、その濃度が約9%に上昇します。しゃっくりが止まる時の濃度は7~8%です。つまり、全力疾走するとしゃっくりが止まる可能性が出てきます。
私は全国の小中学生にこのチャレンジをして頂けないか、といつも考えております。
実際に走ってみた方がいらっしゃいましたが、ご連絡をお待ちしております。
上記3つの仮説は、まだまだ筆者の脳内妄想の段階です。しかししゃっくりの研究を通じて、哺乳類の特性や摂食メカニズムなどについて、まだまだ未知の分野が存在することが見えてきたような気がします。これからも研究と情報発信を細々と続けていければと考えています。